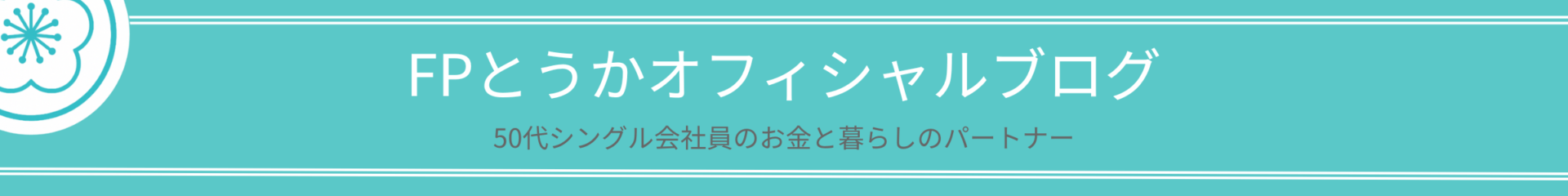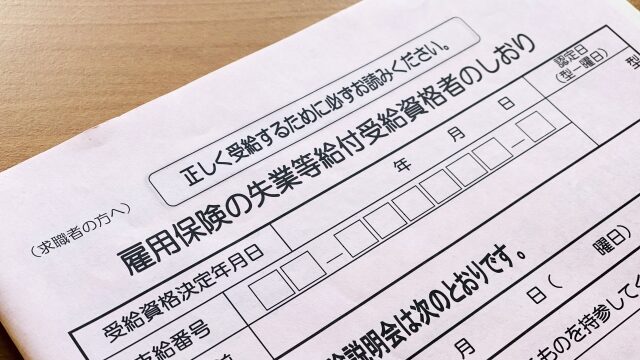公的年金は60歳以降の継続勤務や任意加入制度を利用して金額を増やす方法があり、また基本は65歳から受給開始ですが、繰り上げや繰り下げ支給などを選択して様々な受け取り方がある事をご案内しました。
さらに、個人が任意で加入する私的年金で年金を増やすことで、税制面でメリットを受けつつ、リタイア後の安心な暮らしを準備できます。50代になった方でもまだ間に合います。私的年金の種類やその特徴など基本事項についてご説明します。
私的年金とは?
私的年金は、加入義務のある公的年金とは異なり任意で入れるもので、将来の年金受取額を増やしたい場合に加入します。
私的年金は様々な種類がありますが、大まかに2種類に分かれます。
- 企業が主体の年金制度:会社の規程や福利厚生で定められていて、その枠内でさらに個人が任意で加入ものもあります。
- 個人が任意で加入する年金:個人が任意で加入するものになります。
私的年金には加入方法がいくつもあり、運営する母体としては保険会社や銀行、証券会社などがあります。
企業が主体の年金制度
私的年金の種類は大まかに企業が主体、個人が任意で加入の2種類とお伝えしましたが、まずは企業が主体で規程や福利厚生で定めている年金制度は具体的には以下のような物があります。
- 企業確定給付型年金(DB)
- 企業型確定拠出年金(DC)
- 退職一時金の年金払い
- 財形(年金)
企業確定給付企業年金(DB)
確定給付企業年金(DB)は、企業が従業員の将来の年金額をあらかじめ設定し、退職後にその金額を支払う制度です。年金資産は企業で外部との契約を元に一括運用されます。
そのため運用リスクは企業が負うため、万が一のマイナス時は企業が補填し、定めた年金を従業員に支払います。
企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業型確定拠出年金(企業型DC)は企業が定めに応じた掛金を拠出し、加入者(従業員)がいくつかある運用商品から自分の判断で選択し、運用する企業年金制度です。運用リスクは加入者が負い、運用成績によって将来の年金額が変動します。
掛金は企業側が負担しますが、加入者が任意で上乗せ拠出できる「マッチング拠出」を導入している企業もあります。
退職金の年金払い
会社の退職金制度によっては、決まった額の一部/全部を社員の選択により一時金か年金払いで受け取れることもあります。
企業で福利厚生として定めている退職金、退職年金規程により様々ですので、まずはご自身の会社の定めを(具体的な金額や受取方法はどのような種類があるか)ご確認ください。
なお、退職金を一時金で受け取る場合は、勤続年数が長いほど税額が安くなります。その制度も活用しつつ、一時金と年金の受取額のバランスを検討することも大事です。
ちなみに、労働基準法上では退職金を支給しなければならないという義務はないのです。
しかし、お勤めの会社に労働契約書や退職金規程があり、自分が該当するのに支払いが無いなどのトラブルがあった場合は、まずは会社に支払いの有無を、無しとの場合はその根拠を確認し、会社側の説明が納得できない場合は、労働基準監督署にご相談いただくことをお勧めします。
財形(年金)
会社によっては福利厚生の一つとして財形制度を設定していて、一般、住宅、年金の3種類があり、積立額の上限などが定められています。
財形年金は、会社員が老後資金を準備するための制度です。給与から天引きで積み立てを行い、利子や運用益が非課税となる特徴があります。
個人が任意で加入する年金
個人が任意で加入する年金制度には以下のようなものがあります。
- 国民年金基金
- iDeCo(個人型確定拠出年金:イデコ)
- 個人年金保険
国民年金基金
国民年金基金は基本的に自営業者などの20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者が、加入対象者となる私的年金制度です。厚生年金に加入している会社員は該当しないです。
また、60歳定年時に再雇用とならず完全リタイア、あるいは厚生年金に加入しない程度のスポットワーク的なお仕事を選択した時点で、国民年金の満額(480月)に満たない方がその不足する期間を満たすため、国民年金の任意加入被保険者となった場合は上乗せで加入できます。
国民年金(老齢基礎年金)だけでは老後資金は不足しますのでそれを補うための備えとして活用できます。
iDeCo(個人型確定拠出年金:イデコ)
iDeCoとは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つです。 こちらは自営の方も、勤め人の方も、その被扶養者(主婦/主夫)も加入できます。
加入は任意で、加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てをご自身で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。
掛金は所得控除され、運用益も非課税、受け取りの際も税額の優遇なあるなどメリットもあります。その一方で掛金も属性(会社員の場合、専業主婦/主夫の場合など)で細かく定められており原則60歳以上で年金受給を開始できるなど、自由度が若干低いという特徴があります。
個人年金保険
個人年金保険は、老後の資金を準備するための保険商品です。契約者が一定期間保険料を支払い、60歳、65歳など契約した所定の年齢から年金を受け取る仕組みです。
契約毎に、運用方法については外貨建てや変額保険など、受取方法についてもバリエーションに富んでいます。ちなみにシングルには該当しないですが、夫婦保険という契約もあります。
保険料については所得控除の対象となり、また積立時に死亡した際には死亡給付金が支払われる事が多く、万が一の死亡リスクにも備えられたりします。
今回ご説明した内容は単なるさわりにすぎませんが、個人的な年金対策は、財形年金に加入し、ほぼ定められた上限まで積み立てをしました。さらにiDeCoの口座をつくりそちらの積み立てを始めたところです。
各制度の詳細や、どのように加入を検討すれば良いかは、また別の機会に複数回に分けてご説明したいと思います。