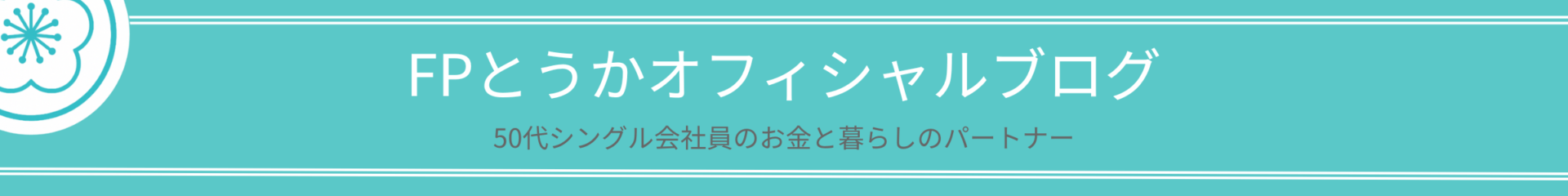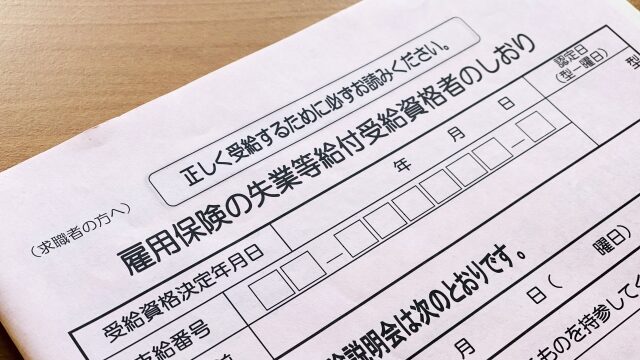生活の3つの柱、衣食住。うち衣と食については、よほど人里離れた地でない限り比較的容易に確保できます。量、質共に月々の収入や個人の好みに合わせて贅沢と引き締めのメリハリをつけることも比較的可能です。
残りの一つ、住居については人生の三大費用(教育費、住宅費、老後費)に入っているくらい大きなお金が動く可能性があります。
シングルですと三大費用のうち教育費は考えなくても良いものの、住宅に確保については財産がそこそこあっても年齢を理由に急にハードルが上がってきたりしますので、早めの対策が必要となります。
二度は来そうなリタイア後の住宅確保問題
シングル会社員が定年を迎えた後、健康状態によって個人差はありますが、住宅確保問題は二度やってきそうです。
ステージ1:体力があり充実した暮らしを実現させる住まい
ステージ2:他者によるケアが必要となった際の住まい
ステージ1の間は充実した暮らしを実現させるため、例えば田舎暮らし、海外移住なども考えられます。
一時期東南アジアで暮せば生活費も安く済むので却って年金が貯められるなんて話もありましたが、円安で世界的に物価が上がっている今では夢のような話。今やそれなりに費用はかかりそうです。
費用がかからない、格安の地域の場合は治安が心配である種のサバイバル能力が問われそうです。
あるいは何らかのお仕事も継続し、ある程度便利な場所に住みたい場合でも、例えば住宅のサイズを考えてみる、通勤の頻度が減るため、公園や病院などの周辺環境を意識した、少し都心から離れた場所にする検討もあるかもしれません。
その一方、ステージ2のケアが必要となった場合の住まいは田舎暮らし、海外移住では医療サービスをはじめとして不安が大きく、人手の確保ができる程度の人口がいる地域での暮らしの方が良さそうです。
もちろん、最初から両方のステージを見越して介護も対応できるシニアマンションなどを検討するのもありだと思います。
あるいは今住んでいる住宅に住み続け、ケアが必要となった際に適宜在宅介護サービスを利用して改修し、自宅でサービスを受けるのも一つの方法です。
(こうなると三大費用のうちのもう一つ、老後費用の方も検討が必要ですが詳細はまた別の機会に。)
既に家を購入している方も、税負担はありますし、マンションならば管理費や修繕積立金などの負担を考慮しないといけないです。
一戸建てを確保しているから管理費も無くて安心・・と思っていても一戸建てならばリフォームや外壁の塗りなおし、屋根や水回りの修繕など、それなりにまとまった費用はかかります。
また、最近は地震や台風などの風水害など自然災害も増え、修繕費や、最悪ケースで建て直しなど、いつ追加で負担が降りかかってきてもおかしくありません。
いずれにしても、少なくとも二度は住む場所確保のために、それなりの費用がかかると想定して貯蓄や保険で備えた方が良さそうです。
家賃が発生しない方法で住む方が安心
家賃が発生する住まいとは、通常の賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅、シェアハウス、公的賃貸住宅などが含まれてきます。
現状ですと通常の賃貸を新たに高齢者、シングルが借りるのはなかなかハードルが高い
です。
資産を持っていたとしても孤独死リスク、保証人問題などで大家さんが貸し渋るなんて問題も聞いたりします。
住宅を持つには賃貸と持ち家どちらが良いか問題をよく聞きます。
費用面トータルですとそう変わらないらしく、好みで決めて良いとの説を不動産のプロから聞いたことがありますが、個人的には定収入が年金のみとなる場合は、隣人トラブルなど問題が無い限りは、家賃が発生しない持ち家を確保しておく方が安心かなと思います。
賃貸の場合は、最低限、年金の範囲内で住居費をカバー出来る状態にしておくことが大事です。
それでも月々の家賃を大家さんに決められるのはちょっと不安です。
需要と供給の関係で、極端な家不足になった際など家賃が無茶なほど増額したり、老朽化による建て直しを機に、不本意な住み替えをしないといけないかもしれません。
『鬼滅の刃』の中で冨岡義勇が、「生殺与奪の権を他人に握らせるな」と言う印象的なセリフがありましたが、家に限らず、ご自身の暮らしを考えるうえで自分が決定権を持つことは非常に大事なポイントです。
賃貸なら公的賃貸住宅も要チェック
公的賃貸住宅とは中堅所得者世帯に対して優良な賃貸住宅を供給するため、主に地方公共団体が直接建設を行い、賃貸している住宅です。
60歳以上を対象とした高齢者向け優良賃貸住宅もあります。賃貸の住宅に住むのであれば、公的賃貸住宅についても調査、検討されることをお勧めします。
ところで、単身世帯が一般世帯の38.1%(2020年の国政調査)と1980年の19.8%と比べて倍増しており、さらに2050年には44.3%に増加すると予想されています。(国立社会保障・人口問題研究所の推計)
先程お伝えした、高齢を理由に貸してもらえなくなるなどの住居問題は、今後は行政の課題として対応し、単身世帯の入居条件を緩和したシングルに優しい住居が増えると予想しています。
また民間の賃貸よりも、単身高齢者向けの様々な行政サービスが受けやすい環境となることも期待できそうです。
シングル会社員は早めに検討に入ろう
定年前にこそ、「どこで」「どんなふうに」リタイア後を暮らしたいかをイメージし、早めに具体的に動く方が良いと思います。
「会社員」の手堅い肩書は、家やマンションを買いやすい、ローンが受けられやすい、しかも厚生年金もあって返済の見通しがつけやすく、退職金での返済も見込めるという素晴らしい信用力を持っています。
逆に会社員でなくなると信用力が急に落ちてしまい、ローンの審査が通りづらい、通ったとしても金利が高めなど不利なことが増えてきます。
賃貸でも同様で、定年間近であっても実際に努めている方は信用力が高く、物件を借りやすいかと思われます。
例えば、田舎暮らし、海外移住など別の土地に住むことを考えている場合でも急に生活全てを変えるのではなく、まずは旅行を兼ねてお試しで季節ごとに民泊してみたり、リモートワーク出来る方は短期で移住してみる事をお勧めします。
その地域の店で買い物をし、お住まいの人と話をしてみてその雰囲気、移住の方にオープンな環境か、季節の寒暖などご自身に合った場所を比較検討するのも良いと思います。
場合によっては、今お住まいの慣れた場所で、住居はダウンサイズしつつ確保しておき、しばらく二拠点生活とした方がいいかもしれないです。
実際住んでみて想定した暮らしと違った場合、帰る場所を確保してあれば比較的楽に撤退できます。
住まいのサブスクリプションサービスも充実してきていますので、定住場所+αといった選択もお試し居住には良いかもしれません。
住み替えに伴って、身の回りの持ち物の見直し、いわゆる断捨離も体力のあるうちにしっかり実行できそうです。