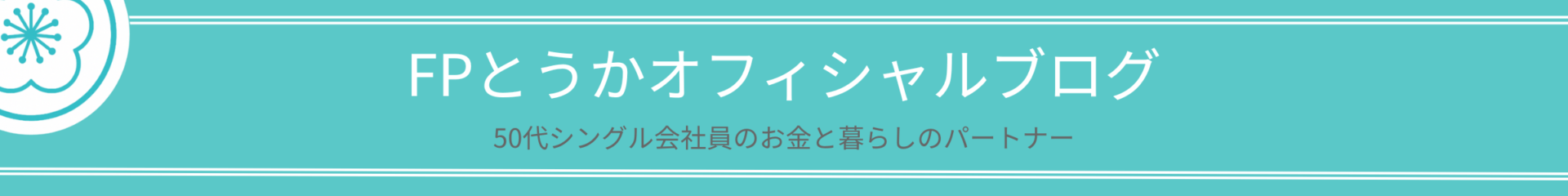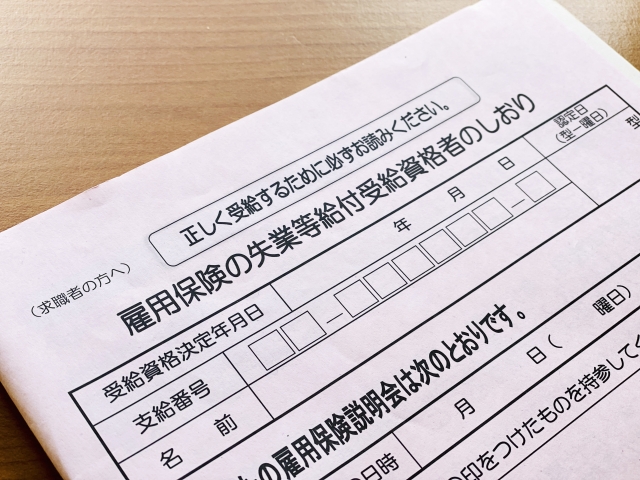定年退職した後は、失業給付を貰おうかと考えている皆様に、特にお気をつけいただきたいポイントを3点ほど絞ってお伝えしたいと思っています。
- ”働く意思と能力”が無いと失業給付は貰えない
- 失業給付は1年以内に貰いきろう、あるいは延長
- 実は65歳少し前の退職の方がお得、でも早まらない!
まずは世に”失業給付””失業手当”と言われる物ですが、今回ご紹介するのは雇用保険の求職者給付のうち「基本手当」というものになります。
それ以外にも雇用保険の事業では教育訓練給付など、お得な制度はあるのですが今回は失業給付に焦点を当てますのでまたの機会にご説明いたします。
おそらく50代シングル会社員の方は、1年以上雇用保険に加入している方かと思いますので、基本的な受給要件はクリアしている状態だと想定し、以下のご案内をいたします。
”働く意思と能力”が無いと失業給付は貰えない
おそらく誤解がありそうなので要注意ですが、「退職すれば全員失業給付を貰えるわけではない」のです。以下は厚生労働省HPからの抜粋です。
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
- 積極的に就職しようとする意思があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
このため、例えば次のような方は、受給することができません。
妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない、就職するつもりがない、家事に専念、学業に専念、会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークで御確認ください)、自営業の方など。
ハローワークで手続きの際に、”ちょっと体の調子が悪いのでしばらく休もうかと・・”と言うと失業の状態とは判断されず、基本手当の対象とはなりません。”体力も落ちてきて長時間の通勤は無理なので、通勤の楽な家の近くで仕事を探したい”は、働く意思と能力はあるとみなされる可能性大です。
失業給付は1年以内に貰いきろう、あるいは延長
「働く意思と能力」の話を聞いて、ちょっと骨休めしてから失業給付を貰う手続き(求職申込)を始めればいいか、と思った方は受給期間にご注意下さい。
失業給付は「離職日の翌日から1年以内」に受給を終えないと、それを過ぎた分は貰えないのです。
例えば20年以上被保険者期間がある人の失業給付の受給日数は150日です。それに、手続き上の給付制限期間2か月(定年の場合は約60日)、待機7日もありその合計は約217日です。
ただし、離職日の翌日にすぐにハローワークに手続きに行ける訳ではなく、会社が手続きを取った書類を受領してからになります。それまで、1か月近くかかる可能性もあります。
そうすると217日+1か月(約30日)=247日
1年を365日と考えると120日程度の猶予はあるものの、諸々の書類(写真や通帳コピーなど)も集めてハローワークに行くため、意外とのんびりもしてられないのです。
厚生労働省HPでは、「すぐに仕事を探す予定でない方は、雇用保険(基本手当)を受けることができません」と記載してあります。
退職後、ちょっと数週間お疲れ旅行でも・・と計画される場合は、退職してから即お出かけすれば、帰ってきた頃に会社から失業給付の申請書類一式が届いている可能性があります。(何か不備の無いように、退職諸手続きは慎重にお願いします。)
世界一周クルーズなど長期の旅行、あるいは長年の疲れを取るべく本格的な湯治でもっと長い期間のんびりされたいと思われている方は、まずは受給期間の延長届を出して、その後にお出かけ下さいませ。
延長手続きは退職日の翌日から2か月以内となっております。会社から書類を受け取る頃、既に退職から1ヶ月くらい経っているとしたら、さらに時間がありません。最優先でハローワークに行って手続きをしてください。
本来の受給期間1年間に求職申込みをしない期間を加えることができ、仕事を探せる状態になった後に、雇用保険(基本手当)の受給手続ができます。
また、受給期間に加えることができる期間は、最大1年間です。
実は65歳少し前の退職の方がお得、でも早まらない!
定年後再雇用や定年延長などで65歳で退職される方は多いかと思いますが、雇用保険の制度の上では65歳未満と65歳以上で区切りがあり、貰える金額はかなり違いがあります。
雇用保険の給付だけを比較しますと、断然65歳未満がお得になります。
<65歳未満: 失業給付(雇用保険の基本手当)>
失業給付は雇用保険の加入期間に応じて、基本手当日額(退職時の給与の50-80%、年齢によって上限額あり)の以下の日数分貰えます。
1年以上10年未満:90日
10年以上20年未満:120日
20年以上 :150日
※上記は定年や自己都合の場合、会社が倒産した場合や解雇の場合など理由が違うともっと給付日数が多いです。
<65歳以上:高年齢求職者給付金>
65歳を超えて退職する場合は、高年齢求職者給付金という一時金に変わります。加入期間により以下の日数分貰えます。
1年未満:30日
1年以上:50日
なお、給付の前提の「働く意思と能力があること」はどちらの給付でも、何歳でも同じです。
以下は一例です。基本手当日額(給与の50-80%、60-64歳の上限額は7,420円、65歳以上は7,065円です※)の上限の方の場合の目安の給付額になります。※2024年8月1日から1年間の数字、毎年8/1に更新されます。
上限の日額の対象者の場合、以下のような計算で約75万円の違いがあります。
65歳未満:7,420円×150日=1,113,000円(28日毎に支給)
65歳以上:7,065円×50日=353,250円(一時金)
ただ上記を見て、すぐに65歳になる直前で辞めよう!と思うのはまだ早いです。ご自身が務めている会社の定年退職や再雇用の雇用条件をよく確認してからご判断くださいませ。
例えばボーナスの支給があったり、65歳満了まで勤務した場合はまとまった退職金の支払いがあるなど、雇用保険の給付を超える待遇の差が出る可能性があります。そちらを比較、検討して、65歳前に退職しても大きな不利益はないな、と思った時は退職時期を検討してみてください。
ちなみにこの切れ目、以前は60歳未満と60歳以上だったのですが、いつの間にか65歳前後に変わっていました。
自分の知っている知識が古くなっているショックが、FP1級受験のきっかけの一つだったことを思い出しました。