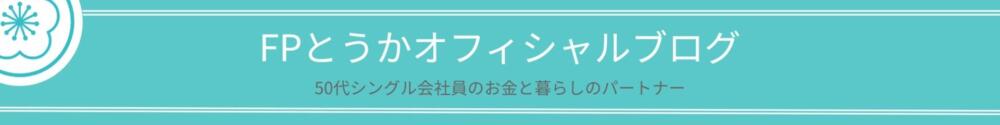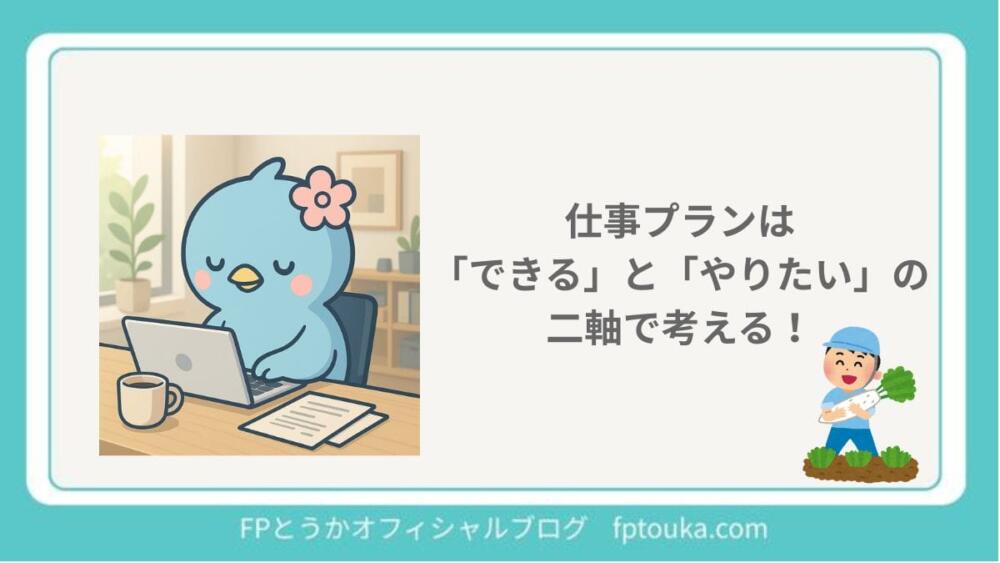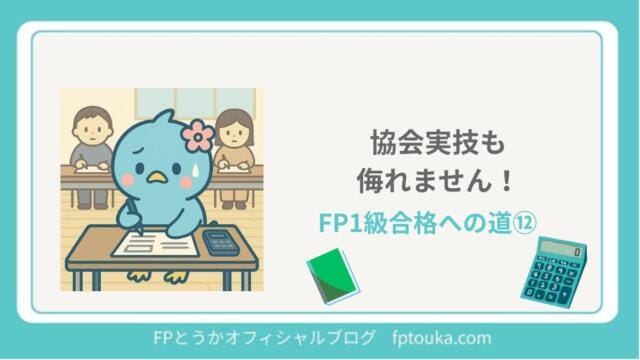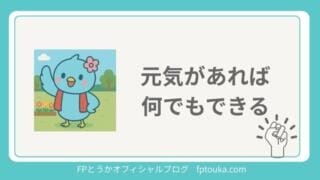前回は会社で50代を対象としたセミナーをきっかけに、定年後はどんなふうに働いていこうか──。そう考え始めました。
やりたい方向性(私の場合は「お金より時間の自由」を重視したいと思いました。)にブレがなければ、ひとつの選択肢に絞らなくていいと思っています。
たとえば今の職場が好きで、再雇用制度も整っている。でも、実際には「希望していた勤務条件ではない」「親の介護が始まった」「自身の健康状態が不安」など、予想外の出来事が起きる可能性は十分あります。
その時のために働き方は一つに固定せず、“複数の選択肢”を持っておくことが、定年後の安心につながると感じています。
仕事プランの2つの基準:「やりたいこと」と「できること」
定年後の仕事を考えるとき、シンプルですが大事にしたいのがこの2軸です。
「やりたいこと」は、若い頃に憧れていた仕事や、趣味を活かしたいという気持ちがベースになります。たとえばカフェ経営や田舎暮らし、動物と触れ合う仕事など。
一方で「できること」は、これまでのキャリアやスキルを活かせる現実的な選択肢です。
この2軸をベースに考えると、自分に合った働き方が見えてきます。
「やりたい×未経験」は、まず体験してみる
「やりたいこと」が未経験分野の場合、ギャップに戸惑うこともあります。
以前、フラワーアレンジメントを習っていた知人が、定年退職後に教育訓練給付金を使って「フラワー装飾技能士」という資格取得し、花屋で働こうと計画していました。しかし、実際は水を含んだバケツや花器が重く、冬の作業場は寒くて厳しい現場だったとのこと。
趣味の教室とスタッフとして働く環境の違いを痛感し、最終的にはその道は選ばなかったようです。
最近はスポットワーク、リゾートバイトなどで定年前に短期体験をする機会もありますので、ちょっとしたお試しで「合う」「合わない」を見極めることもできます。
「できる×やりたくない」は、視点を変えて活かす
一方、「できるけれど、あまりやりたくない仕事」がある場合は、発想の転換が鍵です。
私自身、人事部や社労士事務所での勤務経験がありますが、例えばこれから社労士事務所を開業し、顧客を集め経営するのは正直しんどい…。ただ、その知識を使ってブログ記事を書いたり、経験談を発信したりすることで、違った形で活かすことができています。
「現場でやるのはちょっと・・」でも、「伝える」仕事としてなら活用できる──そんな可能性もあります。
スキルを補って「やりたい×できる」に近づける
「やりたいこと」に必要なスキルや資格がある場合、定年前に少しずつ学んでおくとスムーズです。
私はFPの資格を取り、知識をアップデートすることにしました。元々持っていた社労士資格を眠らせていたのですが、FPの学びを通じて、資産形成、相続などの知識が加わり、ブログ発信にもつなげたいと思います。
とはいえ、ブログの立ち上げにもなかなか苦労していますが、デジタルツールを使いこなすスキルも、これからの時代には必須と感じています。
偶然の出会いも、働き方のヒントになる
仕事は、偶然の出会いで見つかることもあります。
以前読んだ記事では、シルバー人材センターで見つけた「包丁研ぎ」の仕事がきっかけで、マイペースに働き続けている方が紹介されていました。
また、日本語教師を目指す50代以上の方が増えているという新聞記事も印象的でした。国内外で活躍されているようです。
何かにピンときたら、「やりたいこと」の種かもしれません。まずは情報を集め、できれば体験してみる。そんな小さな行動が、次のステップにつながります。
まとめ:「やりたい」も「できる」も、柔軟に持ち合わせて
定年後の働き方に正解はありません。でも、方向性を定めたら、やりたいこと・できること・新たな出会いや偶然をバランスよく組み合わせることで、自分らしい仕事プランが描けると思います。
選択肢は一つに絞らなくていい。定年後はある程度の生活基盤がありますので、大金を元手に始める仕事でなければ、合わないなと思っても、また次を考えればいいのです。
そんな柔軟な心で、定年後もいきいきと過ごせる未来を目指したいですね。