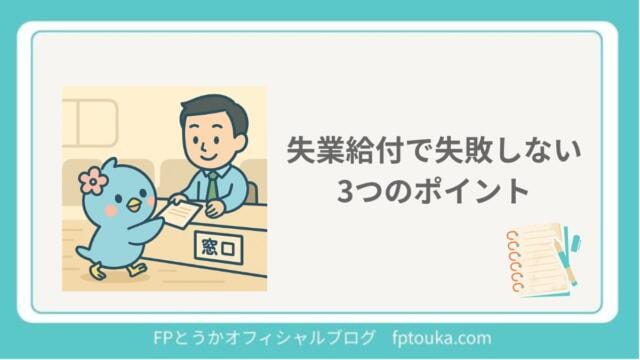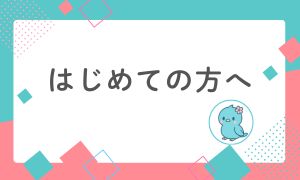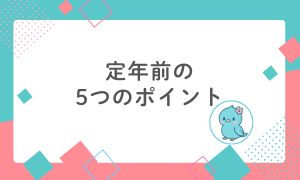60の崖と準備⑥|「資産の崖」減らす不安に負けない資産の使い方

主に50代シングル会社員の定年前後の“気になる不安”に寄り添い、
年金・暮らし・働き方・終活まで制度に基づき解説しています。
実務経験と資格に基づく、わかりやすい情報発信を心がけています。
※この記事は「60の崖と準備」シリーズの第6回です。収入・健康・孤独・役割など、定年前後に訪れる変化を8回にわたって整理しています
はじめに|「資産の崖」は静かに、確実にやってくる
定年後の生活で、多くの人が最初に直面するのが「収入の崖」。 しかし、その後じわじわ効いてくる大きな問題が「資産の崖」です。
毎月の生活費を賄うために貯蓄を取り崩す生活は、頭では分かっていても想像以上に心の負担になります。 「使うのが怖い」「老後が長いから減らせない」という不安は、50代シングル会社員の多くが定年を境に共通する悩みです。
<この記事の目的>老後の資産が“減っていく怖さ”にどう向き合い、安心して資産を活かす方法を解説します。
読者のお悩み整理
- 退職後に貯金を減らすのが怖い
- 年金だけで暮らせるのか不安
- 資産運用はしているが、暴落が怖い
- NISA、iDeCoなど仕組みがよく分からない
- “経験”にお金を使いたい気持ちはあるが踏み切れない
50代独身会社員の多くの方は、現役時代に堅実にある程度の準備はしてあるものの、定年後は築いた資産が減っていく恐怖に直面します。
数字で見る「老後資産」のリアル
まずは、資産の崖の全体像をつかむために統計データを確認しましょう。
●統計上、単身世帯の平均貯蓄は多くない
金融広報中央委員会によると、単身世帯の平均貯蓄額は「941万円」。 しかし中央値は「100万円」。 資産を多く持つ層が平均値を押し上げているため、多くの人の実態はもっと厳しめです。
一方、50代シングル会社員である皆様は、おそらく平均を上回る貯蓄水準+公的年金+退職金が見込める層です。 そのため、「減らすのが怖い」という気持ちがより強く働きます。
参考:「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」(金融広報中央委員会)
●公的年金は“物価に追いつけない”感覚
最近の物価上昇に対し、年金の物価スライドは必ずしも十分ではなく、「実質目減りしているのでは?」という不安も高まっています。 こうした不安が、「資産を使えない心理」をさらに強くしています。
お金を減らす怖さ|心理的ダメージは想像以上
定年後は収入が途絶え、貯蓄が減っていく生活になります。 すると、次のような“心理的ストレス”を抱えがちです。
- 減るのを見ると落ち着かない
- 再び稼げる見込みが薄く、使う勇気が出ない
- 医療・介護の「未知の支出」が怖い
- 長生きしたら破綻するのではないかという恐れ
しかし、お金を減らさないことが正義ではありません。 ビル・パーキンス著『DIE WITH ZERO』にもあるように、お金は「経験」に変えてこそ価値があるのです。
現実の数字から見る「取り崩し生活」
総務省「家計調査」によると、65歳以上単身世帯の年金収入は平均月14.5万円。(老齢厚生年金+基礎年金) 一方、生活費は17万円前後の支出が発生しています。
上記はあくまでも統計の数値で、年金額も生活費も個人差がありますが、毎月数万円の赤字=資産の取り崩しが前提となります。 この構造は、多くの方に当てはまる現実的な姿です。
“資産は減って当然” そう理解することが、資産の崖に怯えず暮らす第一歩です。
資産を“減らさず守る”から“生かす”へ
老後資産はただ「守るため」だけに存在するのではありません。 安心を得るため、経験を積むため、生活の質を保つために使うものです。
●60代前半は「経験への投資」の黄金期
- 健康があるうちに行ける場所へ行く
- やりたい趣味は未来に回さず今やる
- 学び直しで刺激を得る
- 推し活で人生の彩りをつくる
人との交流も生まれ、孤独のリスクも下げられます。 資産には生きた使い方があるのです。
安心して使うための「仕組みづくり」
①キャッシュフロー表を作る
定年後の年金・生活費・医療費・税金の見込みを「年単位」で整理してみます。その際は、物価上昇も織り込みましょう。
老後資金の土台となる公的年金の仕組みについては、公的年金は「保険」|50代が誤解しがちな仕組みと本質をわかりやすく解説も参考にしてみてください。
②お金を3つに分ける
- 必要生活費(固定費)
- ゆとり費(趣味・推し活・旅行・交際費)
- 老後防衛資金(医療・介護・終活費用)
まずは年金は必要生活費に充てることとし、それ以外の生活費補填分、ゆとり費など目的別に口座を分けておき、特にゆとり費は年間予算を決めることもお勧めです。
③「使うルール」を作る
- 生活費2年分は現金で確保
- 口座を必要生活費用、老後防衛資金用などに分けて管理する
- 年間3〜4%以内の取り崩しにする
- NISA口座は「最後まで触らない」
ルールは安心を生み、行動しやすくしてくれます。例えば必要生活費用はリスクの少ない方法(定期預金など)で管理、老後防衛資金はNISA口座とし、元気なうちは手を付けずに配当金は生活費に回さず再投資をする、という分け方も一つのアイディアです。
そもそもの収入がどのくらい変わるのかを押さえておくと、資産の使い方も見通しやすくなります。定年後の収入の高低差については、60の崖と準備①|定年後の「収入の崖」と備え方で整理しています。
安心を保ちながら資産を活かす方法
- NISA、iDeCoの活用:投資、私的年金の準備をするなら、お得な制度を活用する
※iDeCoは私的年金が目的ですが、掛金、運用益、年金で受給する場合も税優遇があり
ルールは面倒ですが50代シングル会社員が始めても遅くはないです。 - 退職金の配分:投資、一時払いの終身年金、生活防衛資金など 分散して老後資金に
- 自宅を賃貸:定年前の住まい/住まない実家を賃貸にし家賃を年金の上乗せに
老後の資産管理は「仕組み × 心がまえ」がセットで必要です。特に、定年を機に資産が減る心配のあまり慣れないハイリスクな投資を始めるのは危険です。
投資は無理に始める必要はないですが、始めるつもりであるなら、現役会社員のうちから知識と経験を積むことをお勧めします。
FPとうかの場合|“経験への投資”を意識し始めました
私自身、今まではNISAやiDeCoなど「増やすこと」を中心に考えてきました。
以前から親が「山寺(山形県)に行きたい」と言っていたのに、気づけばもうあの1000段を超える階段を上れない状態になっていたことに気づきました。(本気で鍛えれば、まだ間に合うかもしれないですが。)
その時、「使えるうちに経験に使ってこそ、資産の価値だ」 と痛感しました。
今は休暇が取れる日は積極的に出かけています。 災害、病気、介護──人生はいつ「それどころじゃない時期」が来るか分かりません。
後悔しないよう、資産は動けるうちに「経験」と「安心」に変える。 この考え方が、資産の崖を優しくしてくれます。
まとめ|資産は“安心”と“経験”のために使う
「資産の崖」とは、貯蓄が減ることそのものではなく、 減る怖さによって人生の行動が止まってしまうことです。
50代の今こそ、
- 収支の見える化
- 目的別のお金の仕分け
- “生き金”として使う発想
これらを整えるチャンスです。 資産は減らすためではなく、あなたの「人生の質」を上げるためにあります。
「資産の崖」は準備次第で“怖い崖”から“安心の坂道”へ変えられます。
この記事を書いた人
FPとうか
ファイナンシャルプランナー1級/社会保険労務士試験合格者。
50代シングル会社員向けに、老後資金・働き方・学び直しなど「これからの人生を整える情報」を発信しています。
▶ このシリーズのまとめはこちら(60の崖と準備まとめ)
老後のお金を考えるときに役立つ記事
公的年金は「保険」|50代が誤解しがちな仕組みと本質をわかりやすく解説
60の崖と準備⑥|「資産の崖」減らす不安に負けない資産の使い方