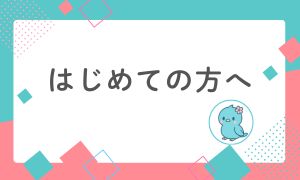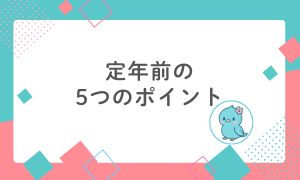60の崖と準備⑤|「居住の崖」空き家・住み替え・地域適応の備え

主に50代シングル会社員の定年前後の“気になる不安”に寄り添い、
年金・暮らし・働き方・終活まで制度に基づき解説しています。
実務経験と資格に基づく、わかりやすい情報発信を心がけています。
※この記事は「60の崖と準備」シリーズの第5回です。収入・健康・孤独・役割など、定年前後に訪れる変化を8回にわたって整理しています。
はじめに:家そのものと「地域との関係」、両方に備えが必要です
50代シングル会社員にとって、定年後の「どこに・どんな形で住むか」は、老後の安心を大きく左右します。
持ち家でも賃貸でも、「家さえあれば安心」とは限りません。空き家化のリスク、固定資産税の負担、年齢を重ねるほど難しくなる住み替え、そして新しい地域になじめない不安など。
これらの要素をまとめて、ここでは 「居住の崖」と呼んでいます。
結論から言うと、居住の崖は「住宅そのものの問題」と「地域・暮らし方への適応」の二重構造です。
<この記事の目的>会社員としての信用力がまだある50代のうちに、情報収集と出口戦略を考え始めることが、老後の安心につながります。
読者のお悩み整理|こんな不安はありませんか?
50代シングル会社員の方からは、次のような声をよく耳にします。
- 「親の住む実家をどうするか、そろそろ考えないと…と思いつつ、手つかずのまま」
- 「今の自宅は気に入っているけれど、駅から遠くて、歳を取ったあとも暮らせるか不安」
- 「定年後は人の少ない地域でのんびり暮らしたい一方で、病院やスーパーから遠いのは怖い」
- 「住宅ローンがまだ残っている。退職までにどこまで繰上返済すべきか分からない」
- 「ひとり暮らしなので、自分が施設に入ったり亡くなったら、家はどうなるのかイメージできない」
どれも「いつか考えないと」と思いつつ、日々の忙しさに押されて先送りしやすいテーマです。
ですが、空き家問題・高齢単身世帯の増加・地域コミュニティの変化など、社会全体の状況も待ってはくれません。
FPとうかの解説:居住の崖とは何か?
「居住の崖」とは、定年前後を境に、 ①家そのものの扱いが難しくなることと、 ②地域や暮らし方になじめなくなることが続けて発生する現象を指しています。
少し分解してみると、次のような要素があります。
- 空き家の増加・引き継ぐ人の不在(実家・自宅どちらも該当しうる)
- 定年後はローンやリフォームの資金調達が難しくなる
- 地域の交通インフラ縮小により、買い物・通院が一気に不便になる
- 地域のコミュニティや情報流通(LINE・自治体アプリ等)に乗り遅れる
つまり、「家はあるのに安全・快適に暮らせない」「地域はあるのに居場所がない」という状態が、居住の崖の実態です。
住まいの選び方は、人との距離感や孤立リスクにも直結します。定年後の人間関係の変化については、60の崖と準備③|定年後に迫る「孤独の崖」とその備え方も参考になると思います。
図表や例で見る「居住の崖」|データと選択肢
空き家と高齢単身世帯の現実
まず、日本全体の状況をざっくりデータで押さえておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全国の空き家戸数 | 約900万戸(空き家率13.8%で過去最高) |
| 高齢者の単身世帯割合 | 65歳以上がいる世帯のうち約3割超が単身世帯 |
| 今後の見通し | 地方や郊外を中心に「引き継ぐ人のいない家」が今以上に増える見込み 都心中心部と地方では利便性、居住費にかなりの差が発生する |
| 空き家対策特別措置法 | 管理不全空き家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が外れる |
| 固定資産税への影響 | 小規模住宅用地(200㎡以下)は通常評価額1/6だが、特例が外れると税額が最大6倍に |
ポイントは、「家を持っている=安心」ではなく、「適切に管理・活用しないと負債化し得る」ということです。
参考:住宅・土地統計調査 2023速報(総務省)
出口戦略のイメージ例
自宅・実家が将来「空き家候補」になりそうな方は、ざっくりでも出口戦略を考えておくと安心です。
| 出口戦略 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 売却 | まとまった資金を確保できる/管理の手間や固定資産税から解放される | 立地・築年数によっては希望額で売れないことも。現役のうちに動くのが前提 |
| 賃貸・リースバック | 家賃収入を得つつ、場合によっては自分も住み続けられる | 管理や修繕の手間・コスト、空室リスクへの理解が必要 リースバックは不利な契約とならないよう注意 |
| 空き家バンク等の活用 | 移住希望者や地域活性化の取り組みとマッチする可能性 | エリアによって需要に差が大きく、時間がかかるケースも |
| 寄付・信託・死後事務委任 | 自分の死後の手続きを信頼できる第三者に託せる | 費用負担や契約内容の確認が重要。専門家との相談が前提 |
「とりあえず今は住めているから」と何も決めないまま時間が経つと、体力・判断力・資金力が落ちてから一気に行き詰まりがちです。
50代の今のうちに、ざっくりでも「自宅」「実家」それぞれの出口の候補を持っておくだけでも、心の負担はだいぶ軽くなります。
注意点|定年後に一気に動こうとしない
居住の崖を前にして、特に注意しておきたいポイントを整理します。
- ローン・リフォームは「会社員の信用」があるうちに
退職後はローン審査が厳しくなり、思ったような住み替えや大規模リフォームができないケースが増えます。 - 実家問題は「親や兄弟が元気なうち」に方向性だけでも共有を
いざ相続が発生してから動き出すと、片付け・売却・登記変更などで心身ともに消耗します。 - 持ち家 vs 賃貸の二択で考えない
ライフステージによって「いったん賃貸に出す」「コンパクトな持ち家に住み替える」など、状況に合わせたプランをいくつか持つのがおすすめです。 - 地域との関係は“いきなりゼロから作らない”
完全リタイアしてから突然移住し、そこで一から人間関係を作るのはなかなかの難易度です。
居住の崖への備え方|50代からのチェックリスト
ここからは、50代シングル会社員が今からできる具体的な備えをチェックリスト形式で整理します。
1. 現在の住まいの「棚卸し」をする
- 立地(最寄り駅・バス停、病院、スーパーまでの距離)
- 建物の状態(築年数・今後必要そうな修繕箇所)
- 住宅ローン残高と完済時期
- 将来「ひとりで暮らし続けられるか」のイメージ
2. 実家(親の家)がある場合は「出口」を意識する
- 今後住み継ぐ予定があるかどうか
- 固定資産税や管理の負担を誰がどう負うのか
- 売却・賃貸・空き家バンク等の情報をざっくりチェックしておく
3. 生活圏のシミュレーションをしてみる
- 車に乗れなくなったとき、今の場所で暮らせるか
- 徒歩・自転車・公共交通だけで1週間暮らす「実験」をしてみる
- 通院・買い物・役所手続きの動線を改めて確認する
- 地方移住を考える場合は、季節を変えて短期の”仮移住”をしてみる。
4. 住み替え・リフォームの方向性を「ざっくり決めておく」
- この家に住み続ける前提でバリアフリーや水回りを整えるか
- コンパクトなマンションに移るか
- 「トカイナカ」(都市と田舎の間のようなエリア)を候補にするか
住宅ローンや固定資産税などの負担は、資産全体の使い方にも影響します。お金の減り方が気になる方は、60の崖と準備⑥|「資産の崖」減らす不安に負けない資産の使い方もあわせてご覧ください。
5. 地域とのゆるいつながりを少しずつ増やす
- 行きつけのお店を1〜2軒つくる
- 自治体の講座やイベントに年に数回でも参加してみる
- 地域情報でよく使われるアプリ・LINEなどに今から慣れておく
どれも「一気に全部」ではなくて大丈夫です。
年に1つずつでもチェックを進めることで、60の崖に近づいたときの安心感がまったく違ってきます。
FPとうかの場合|私自身の居住の崖への向き合い方
都心は美術館やイベント等が多く魅力的ですが、住み続けるには人口の多さ、災害リスクなど考えると躊躇してしまいます。
かといって不便な山あいでの生活もハードルが高い…というのが正直なところです。
そこで今のところのイメージは、程々人が住んでいて、買い物と医療に困らない「“トカイナカ”+状態の良い中古+必要な部分だけリフォーム」といった組み合わせです。
- 駅近すぎなくても良いけれど、バスやタクシーでのアクセスは確保したい
- 徒歩圏内にスーパーとクリニックがあること
- 自分の体力・家事能力に合わせて、掃除や維持が負担になりすぎない広さ
一方で、技術の進歩にもこっそり期待しています。たとえば完全自動運転車が一般的になれば、「駅近」である必然性は今とは違う意味を持つかもしれません。
そうした変化も見つつ、「今の自分の価値観」と「将来の変化の可能性」の両方を頭の片隅に置きながら、少しずつ情報収集をしているところです。
まとめ|居住の崖は「放置すると負債化、準備すれば安心資産」
居住の崖は、 「家そのもののリスク」と「地域・暮らし方への適応リスク」が重なる複合問題です。
しかし、50代のいまから少しずつ向き合うことで、「崖」ではなく「次のステージへの安心な橋」に変えていくことができます。
- 自宅・実家の現状と将来の出口を、ざっくりでも言葉にしておく
- ローン・リフォーム・住み替えは、会社員の信用力があるうちに方向性を決める
- 地域とのゆるいつながりを増やし、「暮らせる場所」の選択肢を広げておく
60の崖シリーズでは、収入・健康・孤独・役割・居住・資産・アップデート・終末と、さまざまな「落とし穴」を見ていきますが、どれも共通しているのは 「気づいたときが一番若い」「備えは早いほどラク」ということです。
あなたのこれからの暮らしが、「不安ベース」ではなく「自分で選んだ納得ベース」になるように、居住の崖とも無理のないペースで向き合っていきましょう。
この記事を書いた人
FPとうか
ファイナンシャルプランナー1級/社会保険労務士試験合格者。
50代シングル会社員向けに、老後資金・働き方・学び直しなど「これからの人生を整える情報」を発信しています。
▶ このシリーズのまとめはこちら(60の崖と準備まとめ)
住まいとお金が気になる方へ