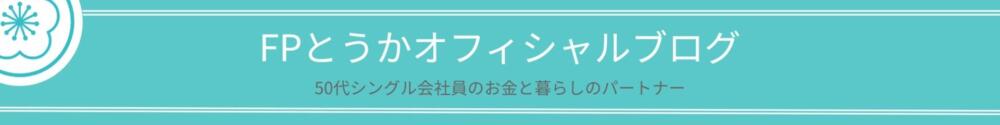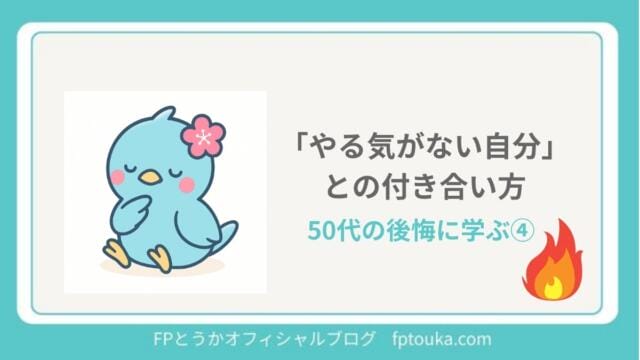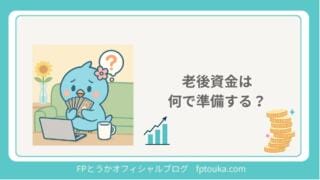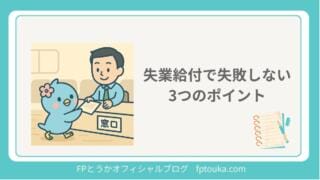桜が満開になる春先は華やかですが、突然の鼻水、喉の痛み、胃の不調、全身のだるさ……そんな不調が気になる季節でもあります。
私も典型的な花粉症で、薬なしではひたすら鼻水が出てしまい、薬を飲めば頭がぼーっとするという体調不良に見舞われました。
そもそも「木の芽時」とは?
「木の芽時(このめどき/きのめどき)」とは、立春から春分頃、文字通り木々が芽吹く時期のこと。古くから「心身が乱れやすく、注意が必要な時季」と言われてきました。
この時期には、気温変動や花粉・黄砂、生活環境の変化などによって、自律神経が乱れやすくなるのです。
そういえば、平成の初めの頃の話ですが、職場では例年、春に元社員らしき人から外線電話が連続してかかってくる日が必ず1日あり、用事は常に”〇〇さんの連絡先を教えろ”といった内容。もちろん教えませんが、その日が来ると「木の芽時だね・・」と仲間とも話していました。
よくある不調パターン
- 肩こり・頭痛、慢性的だるさ
- ふわふわしためまい感、胃腸の調子崩れ
- 集中力の低下、気分の浮き沈み
私自身、鼻水→喉の痛み→食欲減→全身の重だるさ…と順番に不調が襲ってきました。時折花粉の影響で涙も出てくるわ、花粉症の薬でぼんやりするわで、仕事は休まなかったもののかなりな能率ダウンです。
なぜ春先に不調を招きやすいのか?
春先は穏やかで花も咲き、良い季節・・のようですが色々と体調不良を招く落とし穴があるようです。
- 寒暖差:昼夜の気温差で体調管理が大変
- 気圧変化:自律神経の乱れに直結
- 日照変化:生活リズムの崩れ
- ライフイベント:入学・転勤などのストレス
- 花粉・黄砂:アレルギー反応で身体が疲弊
特に寒暖差については、つい昼間の気温に合わせた服装をしてしまい、夜は寒さに震えたりと失敗しがちです。最近は季節先取りには慎重になり、ストールなどは1枚持ち歩くようになりました。
「ゆったり」がキーワード!木の芽時の養生法
中国医学の最古典「素問」によると、春はゆったり過ごすのがポイントのようです。(以下、”黄帝内経素問・四気調神大論”の一文とその現代訳部分を引用しています。)
春三月…此謂発陳。天地倶生、万物以栄。夜臥早起、広歩於庭、被髮緩形、以使志生。生而勿殺、予而勿奪、賞而勿罰。此春気之応、養生之道也。逆之則傷肝、夏為寒変、奉長者少。
『春の3ヶ月、これを「発陳」という。天地のすべてのものが生まれ栄える。夜は寝て朝早く起きて、庭をゆったり歩く。髪や服はゆったりして、志(目標)に心を向ける。生まれても殺さず、与えても奪わず、罰せずに誉める。これが春の気に応る養生の道である。これに逆らえば「肝」を傷め、陽気が沈んだままになって夏に冷えの病になる。』という意味だとか。
髪や服はゆったりして、の部分は楽なカジュアルウエア着用で実践できそうです。仕事中はあまりゆったりした服装はできなくても、帰宅後は楽な恰好が良さそうです。個人的にユニクロのエアリズムコットンのシャツは肌触り良し、通気性良しでお勧めです。
日常でできる「ゆったり」とした実践法
- 朝は少し早起きして、ゆっくり庭を散歩。
- 服装は締めつけない服を選び、エアリズムコットン推奨。
- 花粉対策をして、散歩したり桜を愛でる習慣を持つ。
- 帰宅後はしっかりお風呂、栄養バランスの良い食事を。
- 寝る前にゆったりとした読書やストレッチで心身を整える。
花粉対策に気を付けた装備で散歩などに出つつ、花や景色を愛でて、帰宅後はお風呂で体をしっかり温めて、バランスの良い食事を取り、充分な睡眠を取る。
とにかく”ゆったり”と過ごすのがポイントのようです。
なんだ、花粉症対策以外はどの季節も普通の対策じゃん、と言われてしまいそうな内容になってしまいました。
まとめ:春先の不調は「当たり前」のサイン
春先は桜の華やかさに気を取られがちですが、色々な状況の変化があり体は意外と不安定。木の芽時は「守りの時間」として、無理せず過ごすことで、爽やかに春を楽しめます。
歳を重ねるごとに、体調管理の大切さは増すばかりです。また、一度体調を崩すと元に戻すのにも前より時間がかかる気がします。
どうぞ”ゆったり”過ごす時間を確保し、健やかにお過ごしくださいませ。