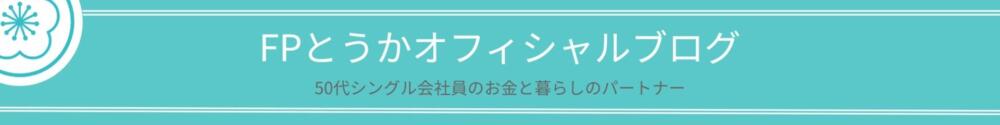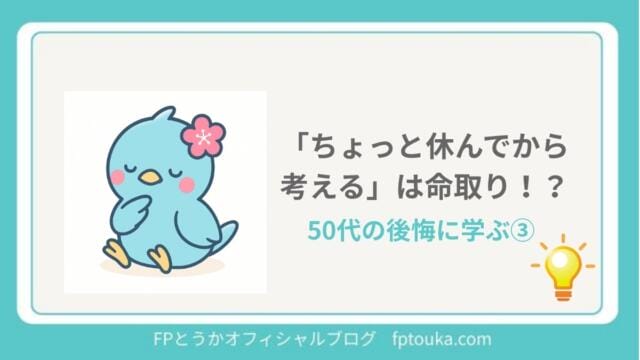50代を迎えた今、日々仕事に追われて忙しくしていても、ふとした時に「このまま一人で老後を迎えるのか」と不安を感じることはありませんか?
特にシングルの方にとっては、健康、人間関係、将来の生活といった漠然とした不安が積もっていきます。その中でも「孤独死」という言葉が頭をよぎる瞬間があるかもしれません。
孤独死は他人事ではない
「孤独死」とは、誰にも看取られず自宅で亡くなり、しばらく経ってから発見されるケースを指します。
かつては高齢者の問題と思われていましたが、近年では50代の現役世代にも増加しています。日経新聞によると、2024年に一人暮らしで自宅で亡くなった人は7万6020人。うち76.4%が65歳以上でした。
私自身も他人事ではないと感じた出来事がありました。2024年12月、ある有名芸能人が自宅の浴室で亡くなられたというニュースを見て、衝撃を受けました。その方は翌日に仕事があったためすぐに発見されたものの、自分が定年後に同じ状況になったらどうだろう、と不安がよぎりました。
早期発見の仕組みをつくる
孤独死の最大の問題は「発見の遅れ」です。家族や友人、地域とのつながりが希薄だと、万が一のときに気づいてもらうまで時間がかかります。
だからこそ、シングルこそ「早期発見につながる仕組み」をあらかじめつくっておくことが重要です。
1. 地域とのゆるいつながり
都心部に住んでいる方ほど、隣人の姿も見たことないという場合は特に珍しくもない話だと思われます。
わざわざお隣のドアを叩いて積極的に深い交流を深めようとしなくても良いと思いますが、住居周辺で出かけるタイミングや、ゴミ出しの際に顔を合わせた際には、会釈や挨拶するなどのちょっとしたコミュニケーションは取れるかと思います。
また、例えば地域での防災訓練や清掃など、慣れていない身には若干気が重いかもしれないですが、機会があって無理なく参加できそうであれば参加しておくのは良いと思います。
また、もう少し積極的な気持ちになれるなら、地域のボランティアやサークルに参加することで、緩やかなつながりが生まれます。最初は単発の活動でも構いません。海岸清掃や花壇の手入れなど、自治体の広報などから興味のある分野を探してみましょう。
2. 定期連絡の習慣化
家族や友人と週1回でもLINEなどでやりとりを習慣化すれば、異変に早く気づいてもらえる可能性が高まります。
私はいずれ、シングル仲間で生存確認のグループチャットをつくりたいと考えています。「おはよう」のスタンプを送りあうくらいならば負担にならないかな、と思っています。
3. 健康管理と医療機関の準備
年1回の人間ドックや歯科や眼科で定期診察は受けておりますが、通院の期間が空いているため、受診しなくても病院から連絡は来なさそうです。
将来のために近隣に「かかりつけ医」を持つ準備も必要だと思っています。通院が途絶えた際に気づいてくれる体制があると安心です。
4. 見守りサービスの情報収集
自治体や企業の見守りサービスは、今後さらに充実していくでしょう。現時点では必要なくても、将来に備えて調べておくことで、リタイア後の安心感が違います。
現在では、宅配の食事サービスに見守りサービスがついている物などもあります。警備会社ではペンダント型の連絡用端末を貸与しているサービスもありますが、万が一の時に駆けつけてくれるサービスは少し高額なようです。
ちょっとした仕事もリスク低減に
数日ごとのアルバイトや副業も、もしかしたら社会との接点をもち、少々のお小遣いが入り、また異変の発見という意味で効果的です。
つい最近では、毎日ブログを更新していた一人暮らしの高齢者の方が、更新が止まったことで異変に周囲が気が付いたという例もありました。
「1.地域とのゆるいつながり」とも重なりますが、実際に誰かと関わる機会を持つことが、孤独死リスクの軽減につながります。
まとめ
孤独死は若い世代であっても、誰にでも起こり得る現実です。仕事が現役のうちは気が付いてもらえそうですが、リタイア後はさらに不安になります。
だからこそ、特にシングルの方は「誰かに早く気づいてもらえる仕組み」を意識し、今から少しずつ準備していくことが大切です。
人とのつながりや情報収集、ゆるやかな安心ネットワークを、自分自身のために構築していきましょう。