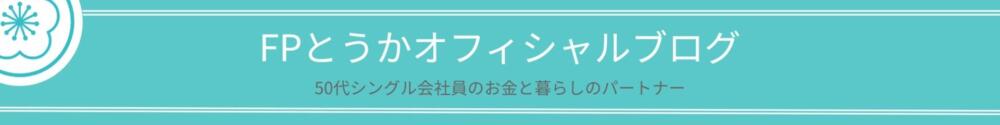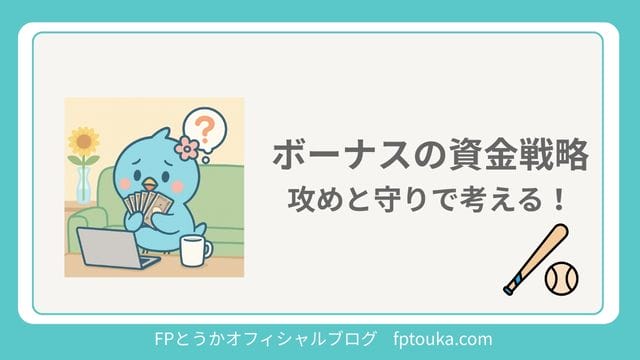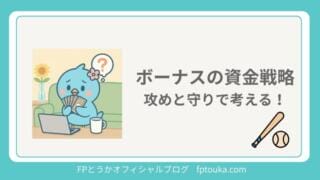前回はボーナスを「攻め」と「守り」の両方から活用するというお話をしましたが、その中でも「守り」の選択肢の一つ、国債についてご案内いたします。
金利上昇が注目される今、「堅実で安全な資産運用」として個人向け国債の人気が再び高まっています。特に購入者の中心は50代・60代とのことです。
この記事では、個人向け国債が選ばれている理由と、3種類の国債の違い・活用法について、FPの視点でわかりやすく解説します。
50代・60代で国債購入者が増加中。その理由は?
報道によると、2025年現在、個人向け国債の購入者の約70%が50代以上で、そのうち過半数が60代。特に人気を集めているのは、17年ぶりに利率が1.00%に達した「変動10年型」です。
購入が増えた主な理由は以下の3つです:
- 利率の上昇:変動10年で1.00%と定期預金の約2倍
- 元本保証の安心感:「国が発行=信用力が高い」との信頼
- 手軽な購入:1万円から、銀行やネット証券で簡単に申込可能
元本保証されて、預金より高い利率が設定されるため、安心を求める年齢層の高めな方々に人気があるのも納得です。
参考:金利高で17年ぶりの利率、個人向け国債 50代以上が購入者の7割(Yahooニュース)
個人向け国債は3種類。それぞれの特徴を比較
| 商品名 | 金利 | 特徴 | 最低保有期間 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| 変動10年 | 年1.00%(変動・最低0.05%) | 半年ごとに金利見直し。金利上昇に対応できる | 1年 | 長期で金利変動にも備えたい人 |
| 固定5年 | 年0.35%(固定) | 5年間は金利が変わらない。中期運用向き | 1年 | 安定した収益を中期で確保したい人 |
| 固定3年 | 年0.20%(固定) | 一番短い運用期間。流動性重視 | 1年 | 短期で安全資産に置いておきたい人 |
個人向け国債のメリット・デメリット
メリット
- 元本が保証される
- 1万円から投資可能
- 1年経過後は中途換金可(直近1年分の利子は差し引かれる)
- 発行元が日本国で信用度が高い
- つみたて感覚でも始められる
デメリット
- 最低1年間は解約不可
- 途中換金すると直近1年分の利子は差し引かれるため、利益が少ない
- 株式や投資信託に比べてリターンは控えめ
- NISAなどの制度を使って購入はできないので、利子に20%の課税あり
- インフレが進んだ場合、実質価値が目減りすることも
ローリスクローリターンな商品ですので、そこまで儲かりませんが安心感はあります。目先に使う予定のないお金の一部を国債で運用するのは、良いかもしれません。
FPとうかの活用視点
以前、50代からの投資デビューは遅くない!賢者の知恵で学ぶ安心の始め方という記事で、著名投資家ウォーレン・バフェットや経済評論家の山崎 元さんが家族に勧めている投資法は「平均を買うインデックス投資」+「国債」という組み合わせでした。
私自身は、今のところ新NISAやiDeCoといった制度を使い、攻めの資産形成(とは言っても投資にはビビりのため、オルカンやS&P500などの”平均”タイプの投資信託を買っています。)がメインですが、NISA枠がいっぱいになった次は、安全志向の資産として国債も検討しようと思っています。
株式投資や投資信託などと違い、変動国債以外は既に金利も決まっているため、大きく儲かる商品ではないですが、満期まで持っていれば損をすることはありません。投資自体が怖くて出来ない・・という方にはお勧めできます。
「当面使う予定のない余剰資金」を置く場所として、定期預金よりは高利回り・低リスクという点が魅力です。リスクはとりたくないけれど、ただ寝かせておくのももったいない──という50代・60代には非常に適した選択肢だと感じます。
まとめ:国債は50代・60代の“堅実な選択肢”
年齢層が上がるほど、資産は「増やす」より「守る」方が安心感が得られます。その中で、個人向け国債は元本保証+適度な金利という両立ができる貴重な選択肢だと思います。
次回は後編になります。「個人向け国債以外」の堅実な資産運用の選択肢──定期預金や保険、社債や債券型投資信託などについて比較・解説していきます。