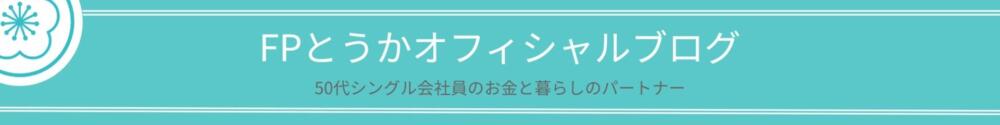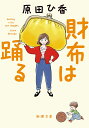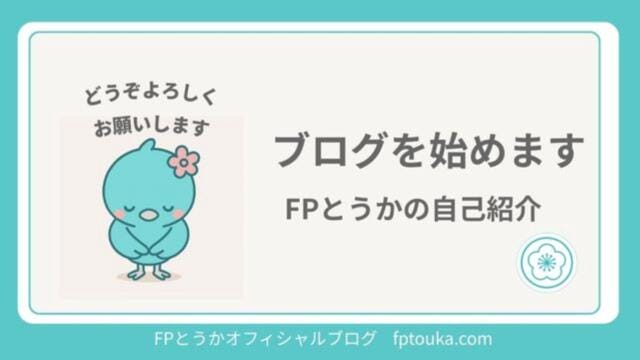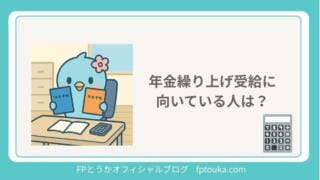「年収は財布の200倍」という法則をご存じでしょうか?亀田潤一郎さんの著書や、原田ひ香さんの小説『財布は踊る』のワンシーンがこの話を思い出させます。専業主婦の主人公がルイ・ヴィトンの長財布を節約の末、とうとう手に入れ、店員から「年収の200倍ですよね」と囁かれる場面が印象的でした。
長財布=お金持ち?その背景は風水?
この説は何となく聞いたことがありましたが、2010年刊『稼ぐ人はなぜ、長財布を使うのか?』(亀田潤一郎著)ではっきりとお勧めいただきました。
ちなみに長財布を使うとお金持ちになるという考えは、一般的には風水や心理的な信念に基づいているのだそう。風水では、お金を扱う「器」や「入れ物」によって金運が左右されるとされています。長財布はお札を折らずにまっすぐ入れることができるため、お金にとって心地よい場所とされ、結果的に金運がアップすると信じられています。
心理面でも、お札を整然と保つ習慣が、無駄遣いを抑制する効果があるのではないかと考えられています。
実際、お金持ちは長財布を使っている?
実際に自分や友人が会った事がある中で、最もお金持ち(大体は企業の創業者です)は、意外にも「財布すら持たない」「マネークリップ」「小銭はポケット」といった方でした。
これは、突き抜けたお金持ちは自らは支払いをするケースがあまりなく、支払いは大体カードや請求書、請求業務を代行してもらうケースが多いためと考えられます。
とは言え、「ある程度の資産がありそうな層」では、長財布の利用率はやや高めのようです。やはり”ピン札”で現金を持っておきたい、年齢層がやや高めな世代が多めなのと、長財布のステータス感も理由の一つでは、と考えております。
キャッシュレス時代の財布事情とリアリティ対策
しかし、キャッシュレスが進む中、財布はより小型化・ミニマル化しています。長年ルイ・ヴィトンを愛用していた友人もいつの間にか長財布からコンパクト財布に乗り換えていました、また、今では若い世代では100均のポーチを愛用している方もいるとか。
キャッシュレス化に伴い、使った金額はただの数字となってしまい、カードや電子マネーでは使った感覚が掴みにくく、気づかないうちに無駄遣いをしてしまうリスクがあります。そこで亀田さんが近年提案されていたのは、あえて現金主義に戻る“アナログ習慣”です。具体的には以下のようなポイントです。
アナログ財布習慣のすすめ
- 長財布+小銭入れを使い分け
- 1円・5円は募金に、小銭の一部を貯金に活用(例:500円玉貯金)
- コンビニなどでは基本的にまず硬貨をチェックし、足りないときは札を出す(「お札を崩してまで買わなくていいか」という意識になる効果)
参考: デジタル時代に、100円玉、50円玉、10円玉を持ち歩く(あるじゃん編集部)
でも、財布より大事なのは“マネーリテラシー”
『財布は踊る』で登場した主人公の夫は、よく考えずクレジットカードをリボ払い設定にしていて、いつの間にか金利で膨らみ200万円超の借金を抱えることになります。その返済のため、主人公が何年もかけてコツコツと貯めたお金で買った、新品のルイ・ヴィトン財布をメルカリで売却する羽目になってしまいます。
そのエピソードは現実に結構ありえそうで、お金についての無自覚がどれほど怖いか教えてくれます。
現代ではキャッシュレス化やオンライン取引が進んだ結果、浪費に対する警戒心が薄れがちです。だからこそ、マネーリテラシーの強化はますます重要です。
FP3級でもリボ払いのリスクは扱われますが、お金に関する基本的な知識を持たずに18歳を超え、成人だからとカードを作れてしまうのはリスクが高いのでは?と思ってしまいます。これから「高校生でも必修授業でFP3級相当の知識を持つべき」と感じるほどです。自分も高校時代に知っていたかった…!
結論:長財布は道具。金運より習慣・知識が強い
- 長財布=金運アップの風水を元にしたスピリチュアル的な側面あり
- 実際に長財布を使っている成功者も多く見たが、絶対ではない
- キャッシュレス時代には「お札・硬貨を感じる習慣」でお金のリアルを感じることが大事
- 財布の形よりも、支払いに対する「意識」とお金の「知識」が最大の資産になる
大切なのは、自分のライフスタイルに合った財布と使い方を選ぶこと。そして、その先には「お金をどう使うか」と共に「お金についてどう考えるか」が資産形成により大きな影響を与えると考えております。