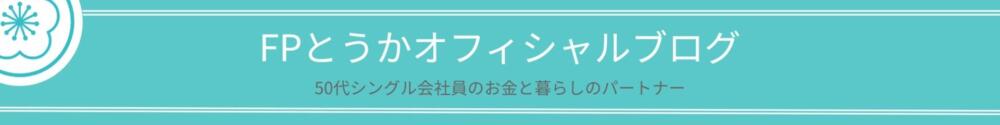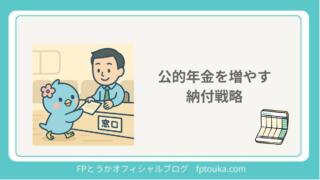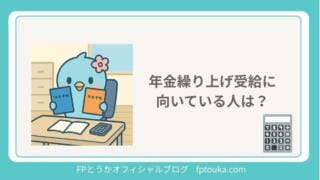公的年金の見込み額を確認して「ちょっと少ないな」と思った方へ。前回は引き続き厚生年金加入して期間を追加したり、任意加入を利用して増やす方法をご案内しましたが、年金を増やす方法として有名なのが「繰り下げ支給」です。この記事では、繰り下げ支給の仕組みと注意点、どんな人に向いているかを解説します。
繰り下げ支給とは?
65歳から受け取る予定の年金を、66歳〜75歳の間で繰り下げると、1ヶ月ごとに0.7%ずつ受給額が増加します。最大で84%の増額が可能です(75歳まで繰り下げた場合)。
また、基礎年金だけ繰り下げ、厚生年金だけ繰り下げという選択もできます。例えば「65歳から基礎年金だけ受け取り、厚生年金は67歳から受給」なども可能です。
年金を増やせる上に、一生その金額が続くというメリットがあります。
参考:年金の繰り下げ支給(日本年金機構)
具体的な金額シミュレーション
例えば「65歳から2年間は基礎年金だけ受け取り、厚生年金は67歳から受給」と、厚生年金を2年繰り下げたときは0.7%×24か月=16.8%増額されます。
厚生年金が120万円/年(10万円/月)の場合、2年繰り下げで140.16万円/年(約11.68万円/月)に増額します。
この例ですと、65歳、66歳の2年は69,308円/月(令和7年の金額)の基礎年金のみ。
67歳からは繰り下げで増えた厚生年金116,800円+基礎年金69,308円で合計186,108円/月。
その増えた金額が一生貰える、というのは安心できるポイントです。
参考:繰下げ増額率早見表(日本年金機構)
繰り下げ支給の注意点
基本的にデメリットは少ないですが、次のようなケースには注意しましょう。
- 繰り下げ中に死亡した場合、遺族が受け取れるのは元の年金額
- 65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金や振替加算が受け取れない
50代シングル会社員の方には、遺族年金や配偶者の加給年金などを気にする必要はありませんので、繰り下げ支給のデメリットは無しと言っても良さそうです。
繰り下げ判断のポイント
再雇用などで収入があるため、年金は繰り下げをしても問題なさそうな場合は、以下のようなポイントを検討してみてください。
- 何歳まで働く予定か?
- 健康状態に不安はないか?
- いつ大きな出費(リフォーム、旅行など)があるか?
繰り下げを何歳まで行うかはライフプランに深く関係します。まずは「〇歳で年金をもらったらどうなるか?」というシミュレーションをしておくのが有効です。
こちらは「ねんきんネット」で試算ができるようになっています。
意外な落とし穴──税金や保険料
公的年金は雑所得扱いのため、受給額が多くなると所得税、住民税、健康保険料、介護保険料も上がります。
年金を増やしても手取りが意外と減ってしまうケースもあるので、他の年金や退職金とのバランスも含めて設計しましょう。
元が取れる年齢と「使える時期」
よくある疑問は「何歳まで生きれば元が取れるのか?」ですが、繰り下げ支給はおおよそ80〜83歳が損益分岐点です。
ただし重要なのはお金を楽しく使える時期。健康寿命とのバランスも考え、「今の生活をどう楽しむか」との兼ね合いが大切です。
亡くなったとき資産額がピークだったという話もよく聞きますが、それでは少し寂しい気もします。個人差はあると思いますが、もしかしたら資産が有効に使える時は75歳より前、いわゆる前期高齢者の時期頃くらいではないのかと思っています。
まとめ
年金の繰り下げ支給は、老後資金を増やす有効な手段です。ただし、自分のライフスタイルや資産状況、健康状態を踏まえて検討しましょう。
次回は、逆に「繰り上げ支給」の選択肢についてご紹介する予定です。