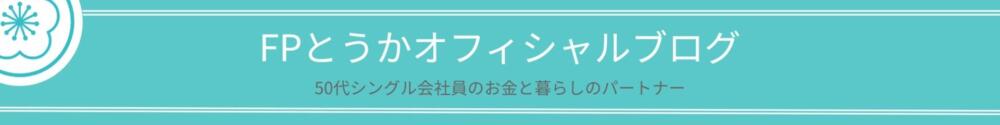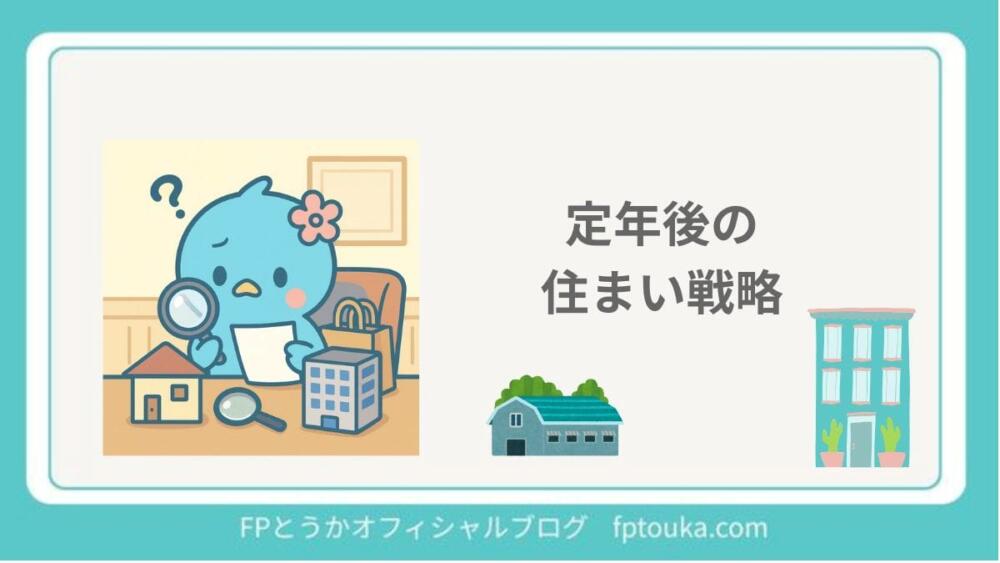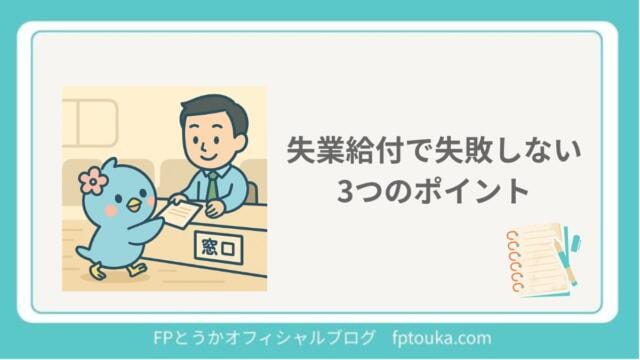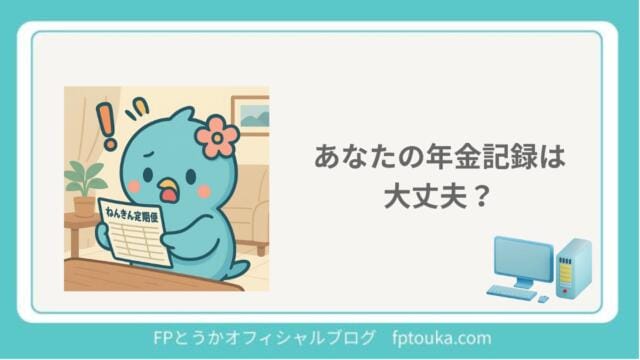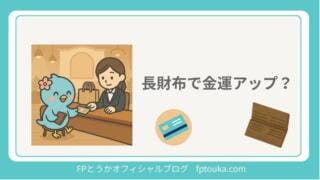生活の3つの柱、衣食住。うち衣と食についてはオンラインで手軽に購入できるので、よほど人里離れた地でない限り比較的容易に確保できます。量、質共に月々の収入や個人の好みに合わせて贅沢と引き締めのメリハリをつけることも可能です。
残りの一つ、住居についてはそう手軽ではなく、人生の三大費用(教育費、住宅費、老後費)に入っているくらい大きなお金が動く可能性があります。
特にシングルで定年を迎える場合、その後に住宅確保が難しくなる可能性があり、早めの計画とできれば定年前に準備が必要です。
住まいは二度やってくる:2ステージで考える
定年後にもステージが2つあり、それに合わせた住居確保が必要となります。
- ステージ1:体力が残り、“充実した暮らし”を実現する住まい
- ステージ2:他者によるケアが必要になったときの住まい
ステージ1では、地方移住や海外生活、一戸建てや都心近郊マンションなどが候補になります。一昔前は東南アジアの国に移住して悠々自適・・といった話もありましたが、円安・物価高の昨今、思いのほか生活費がかかる点には注意が必要です。
一方ステージ2では、医療・介護の拠点が近い住まいが前提になります。シニア対応住宅や、自宅住まいを続ける場合でも、在宅介護リフォームなども選択肢に含まれます。
家賃なし or 賃貸?あなたに合うのは?
賃貸、介護サービス付き高齢者住宅、シェアハウス、公営住宅などは賃料が発生しますが、入居条件・保証人の壁が高く、シングル高齢者には、貸し渋りとまでいかなくても契約が不利となるケースも考えられます。
不動産のプロによれば、「トータル費用は持ち家と賃貸で大差ない」が定説。しかし、定年後に収入が年金に限定されるような場合は、維持費と固定資産税はかかるものの、家賃は発生しない持ち家確保の安心感が大きいでしょう。
公的賃貸住宅という選択肢
公的賃貸住宅は自治体が整備し、高齢者や中所得層にも門戸が広い制度です。特にシングルのシニア世代にとっては、賃貸の貸し渋り対策として要チェックです。
単身世帯は年々増加傾向にあり(2020年38.1%→2050年44.3%)、これから行政も対応強化が進むと期待されます。また、高齢者に対応強化された地域や物件に住むことで、シニア向けの行政サービスの情報を把握したり、実際に利用しやすくなったりします。
家を買うのも借りるのも、定年前がチャンス
会社員であるうちはローン審査が通りやすく、完全リタイアで信用力低下する前に「どこで」「どう暮らすか」を決めておくのが賢明です。
また賃貸契約も、会社員の肩書があるうちの方が借りやすいと思われます。年齢が上がってからの賃貸契約は、資産があって家賃などの支払いに問題ないとしても、ハードルが上がって住みたい物件を借りられないリスクがあります。
ダウンサイズ&断捨離で身軽に
引っ越しをする・しないに関わらず、会社員のうち、あるいは定年後のステージ1の時期に物を整理するチャンス事をお勧めします。年を重ねるほど荷物整理はしんどくなってきますし、荷物を減らすことで住まいのダウンサイジングにつながります。
また、いざ引っ越すことを決意した時にはすぐに行動に移せます。
二拠点・サブスク住宅という選択肢
最近は“住まいのサブスク”やシェア型住居も増加中。特にステージ1の体力があり、あちこちに移動することが可能な時期は良いかもしれません。小さくとも定住拠点を確保しつつ、季節や気分に応じた居住ができる新しい選択肢として注目されています。
田舎や海外移住を考えるなら、短期移住や民泊などで試してみるのも手です。実際に暮らしてみると、想像以上に寒い/暑いなどで気に入らなかったときにも、戻れる拠点があれば安心です。
もしも移住したい地域にサブスク住宅がある場合は、現役のうちに季節ごとの休暇時期などに利用し、移住の予行演習をするのも良いかもしれません。
まとめ:イメージ+行動が安心の鍵
- 定年前に「どのステージで、どんな住まいが理想か」を検討する
- 住みたい地域で持ち家と賃貸、公的住宅のメリット・デメリットを比較する
- 住まいのサブスクなどを利用し試住・二拠点戦略・断捨離など、行動もセットで備える
- 定年後は財産を持っていてもローン、賃貸契約のハードルがあがるため、できれば「会社員」の肩書を持っているうちに契約する
住まいは人生最大の選択のひとつ。シングルの方も早めに情報収集・行動を始め、定年前から住まいの準備を進めることで、安心したセカンドライフが迎えられるはずです。