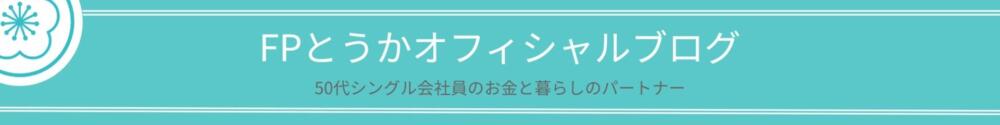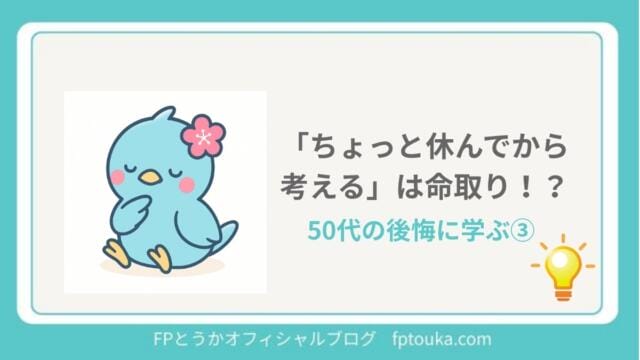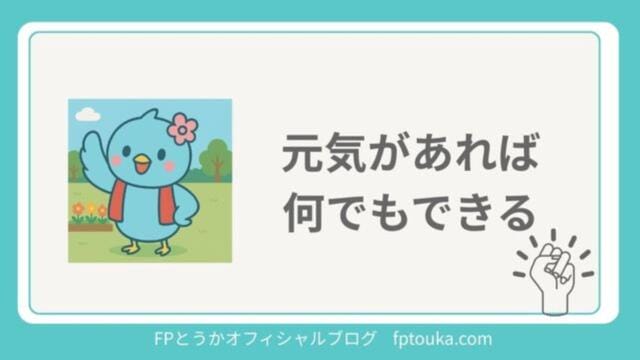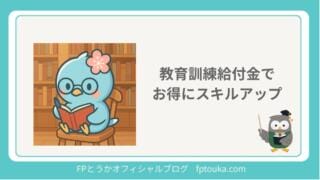取り立てて不幸な出来事があったわけでもないのに、なんとなく心がもやっとする──。
そんな“停滞感”を覚える瞬間は、誰にでもあるのではないでしょうか。
年度の変わり目に周囲が転職や異動で環境を変える中、自分だけ何も変わらないような気がしてみたり。
あるいは、会社の制度で給与が下がるのに業務は変わらない…皆同じ条件で不公平ではないけれど、どこか納得できない、などなど。
そんな感覚に包まれたとき、私が試しているのは「手放す」ことです。
手放すことで空いたスペースに、新しい運が入ってくる
よく言われるのが「古いしがらみを手放さないと、新しい運は入ってこない」という考え方。
これに共感して、私は令和元年の元号が変わる時期の大型連休や、新型コロナでのステイホーム期間中に“断捨離”に取り組みました。
参考にしたのは、あの「こんまりさん」こと近藤麻理恵さんのメソッド。物を手放す基準は”ときめくかどうか”でした。
“ときめかない”洋服や本、書類などを思い切って処分することで、空間も気持ちもスッキリしたのを覚えています。
“ときめかないけど必要”な物との付き合い方
とはいえ、中にはときめかないけど手放せない物もあります。
例えば喪服や、日常で活躍するユニクロのヒートテックやエアリズムなど。
全く心はときめかないけれど、なくては困る存在です。
特に日常使いのアイテムは、ある程度使ったら「今までありがとう」と感謝して、新しい物に買い替えるようにしています。
少しでも快適な素材になっていたりすると、それが小さな“ときめき”につながる気がしています。
“ときめかない習慣”を見直すタイミング
こんまりメソッドは“物”だけでなく、“習慣”にも応用できると聞きます。
例えば、寝る前のスマホチェックや、なんとなくの間食、“〇〇すべき”という思い込みのルールなど。
それらは、今の自分を縛る“ときめかない習慣”かもしれません。
私も最近は夜のブログ作業を優先するようになり、週末の家飲みやドラマ視聴の時間が減りました。
ただ、ブログも「毎日更新しなければ」と決めてしまうと苦しくなるので、マイルールは「できるだけ毎日、5分でもいいのでログインする」。
細く長く、自分のペースで続けることを大切にしています。
ときめかなくても「続ける価値」のある習慣
振り返れば、FP1級の受験勉強は正直まったくときめきませんでした。むしろ自分の記憶力の悪さにげんなりしてくる時もありました。
“毎日やらなければならない”というプレッシャーの中で続けた日々ですが、それは未来の自分への投資だと思うから続いたと思います。
同じように、毎晩寝る前はフロスや電動歯ブラシを使い、丁寧な歯磨きをする習慣があります。これも地味で面倒で、ときめきはありません。でも歯の健康は全身の健康に直結します。
歯周病を予防することが、諸々の生活習慣病の予防にもつながる──そう思えば、地味な習慣も続けようと思えるのです。
重要なのは「それが将来の自分のためになるかどうか」。
ときめかなくても、価値ある習慣は、生活に組み込んでおくべきだと実感しています。
停滞感をリセットする“小さな親切”
ところで、気分が停滞している時にもう一つ私が試しているのは、あえて「ちょっといいこと」をすること。
例えば、道に落ちているゴミを拾って捨てる、トイレの手洗い場の水滴をペーパーでサッと拭く、コンビニの募金箱に小銭を入れるなど。
些細なことですが、人に優しくすると自分の気分もほんのり上向きます。
そうして少しだけ前向きな気持ちを取り戻せると、日常の停滞感も少しづつリセットできる気がします。
まとめ:手放すもの・続ける習慣を見極めて、心を整える
停滞感を感じるときこそ、「何を手放し、何を続けるか」を見直す絶好のタイミングです。
ときめかない物や習慣は思い切って手放してOKだと思います。ただし、将来の自分を支える習慣は、多少ときめかなくても大事に育てていきましょう。
以前に定年後の住まい戦略についての記事も書きましたが、荷物を減らしておくことで住まいのダウンサイジングもでき、理想の住まいが見つかった時には、シングルの身軽さですぐに転居の準備もできます。
物も習慣も、自分自身の気持ちも、うまく整えていくことで、50代からの毎日はもっと軽やかで、充実したものになるはずです。