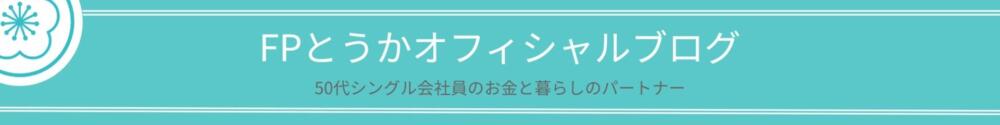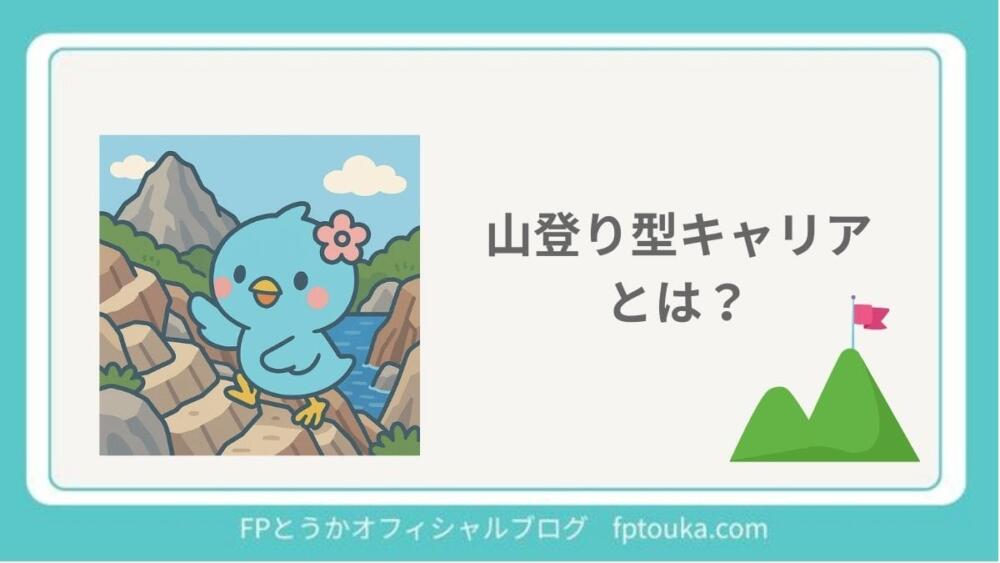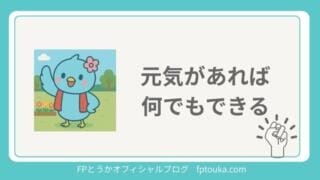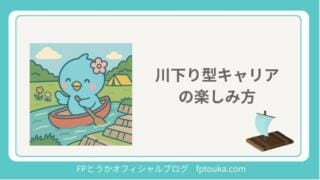「これをやりたい!」という明確な目標に向かい、計画を立てて努力し、ゴールを目指す。そんな人を、私は“山登り型”のキャリアと呼んでいます。
スポーツ選手や研究者に多いタイプで、子どもの頃から夢を抱き、それに向かって突き進む姿は、多くの人にとっての理想像かもしれません。
例えば大谷翔平選手が高校時代に作成した「マンダラチャート」は有名です。明確な目標を言語化し、そこに至るために必要な行動を具体化したその姿勢は、まさに山登り型の代表例です。
あるいは、藤井聡太さんのように、静かな佇まいですが、その勝負強さで圧倒する将棋の天才もその一人です。負けるのが嫌いで、目指す頂に向けて日々努力し続け、無駄なく成果を積み上げていく姿は、まさに「頂上を知る人」です。
山登り型キャリアの強み
山登り型の人は、「自分なりの頂上」が見えているため、努力の方向性がブレません。
たとえばラグビー元日本代表の福岡堅樹さん。トップアスリートとして活躍する中で、医師の道を目指すために引退し、医学部への道を選びました。その潔さと行動力は、目標が明確だからこそできるものです。
また、かつて社労士事務所に勤務していた時に、関わる弁護士事務所にちょっと雰囲気の違う新人弁護士が入られました。トラック運転手として働きながら司法試験の勉強を続け、十数年かけて合格を果たしたのだそう。情熱と持続力、まさに“山を登る力”の結晶です。
でも、全員が頂上に立てるわけではない
ただし、目指したい頂上があっても、誰しもがその頂上に立てるわけではないです。(皆が社長や組織のトップ、金メダリストになれたりはしないですし。)やりたい事、目指す事の周りで頂上付近まで来ても、思う通りの結果にならない事の方が多いです。
その時は少し違うフィールドでの頂上、頂上を目指す人のサポート役になるなど、少し角度を変える方法で目指す方向を変えると、違う景色が見えるかもしれないです。
会社に例えると、社長や役員を狙わず、自分の専門領域でこの仕事は〇〇さんと認識されるようになる。スポーツに例えると、トップ選手にはなれずとも支える側に回る、あるいはご自身の競技経験を活かして大学などでの研究テーマにし、その専門家となる、などです。
万人が分かりやすい事でのトップを目指すではなく、自分で決めた山の頂上を目指していくのも悪くないと個人的には思います。(ナンバーワンでなくても、オンリーワンと言われる方向性です。)
目標があっても山登りとは少し違う
会社の目標管理制度も山登り型前提で作られているケースが多く、「目標を立てて達成する」という形が評価の軸になります。(正直、私自身はあまりしっくり来ていません。)
特に事務系職種は数値化しにくく、日々の業務は淡々と進むことも多い。目標を無理やり立てては「まぁまぁ」でやり過ごす…そんな自分に、どこか後ろめたさを感じることもあります。
とはいえ、ものすごい多忙で、業務効率アップなどの結果を出して、「平均より上」の評価であっても、「平均」の方との賞与の差は大した差では無い・・それなら頑張りすぎず「平均」の評価の方がコスパ、タイパが良いのでは?いう発想も理解できます。
思えば、私の社会人生活は「新卒で入った会社でたまたま人事に配属され、社労士という資格を勧誘電話で知り…」といった流れでスタートしました。明確な目標があったわけではなく、その都度「ご縁」で進んできたのです。
次回:「川下り型キャリア」も悪くない
実は私のように「目標が明確でない人」のほうが世の中には多いのかもしれません。
“川の流れに乗りながら方向を調整していく”ような働き方もあります。それが「川下り型」のキャリアです。
次回は、その「川下り型」の生き方と強みについてご紹介したいと思います。